夜9時。子どもたちが寝てからの数時間こそが、パパの「自分時間」です。
でも、「抱っこ!」「トントンして!」…と要求がエスカレートし、寝かしつけが夜の残業になっていませんか?自分の時間が削られ、イライラが募る—この悪循環は、子どもが「自力で寝る力」を持てていない証拠かもしれません。
僕は以前、看護師として人の睡眠の科学的根拠を学び、今は外壁塗装で合理的な段取り力を磨いてきました。その知識と経験を駆使して確立したのが、我が家の「自力で寝る」ための入眠ルーティンです。
「抱っこも添い寝も一切しない」という、傍から見ると「スパルタ」な方法かもしれません。しかし、これが我が家の4歳と2歳の姉妹をたった数ヶ月で「寝かしつけのいらない子」に変えました。
「甘えさせない」のが真の愛情であると信じる、パパの入眠法をご紹介します。
徹底!自力で眠る力を育むパパ流3つのポイント

この方法は、単にパパの時間を確保するだけでなく、子どもが「自分で自分の感情と体をコントロールできる」という自立心を育むためのものです。寝室でのルールは、この3つだけです。
1. 徹底ルール:寝室に遊び道具を持ち込まない
【寝室は「寝る」以外の機能を持たせない】
このルールは、子どもに「寝室=眠る場所」と明確に認識させるための、最も重要な土台です。
- ✕:好きなぬいぐるみや本を持ち込ませる(遊びの延長になってしまう)
- 〇:寝るためだけのアイテム(布団、パジャマ、水筒など)しか置かない。
もし子どもが玩具を持ち込もうとしたら、「この部屋は寝るために休むお部屋だよ。遊びたいならリビングに戻ろう」と冷静に伝え、すぐに撤収させます。外壁塗装で現場の整理整頓が仕上がりに影響するように、寝室の環境整理こそが質の高い睡眠に繋がるのです。
2. 最重要原則:抱っこや添い寝はしない
【「抱っこで寝落ち」は卒業!自力で入眠できるように見守る】
子どもが寝付くまで抱っこやトントンを続けていると、子どもは「パパ(ママ)の体に触れていないと眠れない」と学習してしまいます。これが、夜泣きや途中の目覚めの原因になります。
元看護師の視点から見ると、人が睡眠中に目覚めるのは自然なことです。その際、寝た時と同じ状況(=パパの抱っこ)がないと、脳が「危険だ」と認識してしまい、再度入眠できなくなります。
僕のやり方は、布団に連れて行き、「パパは大好きだよ。自分で寝るんだよ」と声をかけたら、後は一切手を出しません。最初の数日は辛いですが、子どもはすぐに「布団の上で目を閉じる」という新しい入眠方法を学習し始めます。
3. パパの試練:夜泣きも途中の目覚めも「辛抱強く見守る」
【自立入眠を邪魔しないパパの毅然とした態度】
この方法を始めて一番の試練が、夜泣きや夜中の目覚めです。子どもが泣き叫んでパパを呼んでも、抱っこはしません。
- 夜泣きへの対応:「大丈夫だよ、パパはここにいるよ」と声だけかけます。抱き上げたり、背中をさすったりはしません。
- 辛抱の記録:最初の週は、2歳の次女が30分以上泣き続けた日もありました。しかし、「ここで折れたらこれまでの努力が無駄になる」と決意を固め、静かに見守り続けました。結果、子どもたちは「泣いても誰も来てくれない」と悟り、次第に自分で気持ちを落ち着かせて再入眠できるようになりました。
この「辛抱強く待つ力」こそが、子どもに自分で困難を乗り越える力(挑戦する心)を与えることになります。
まとめ:自立寝は、親子の信頼関係の上に築かれる
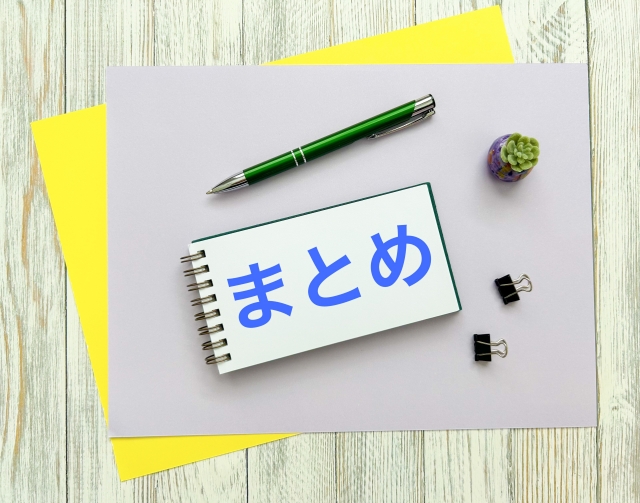
寝かしつけの成功は、「早く寝てくれること」がゴールではありません。
子どもが自分で安心し、眠りにつける「自立心」を育むことが真のゴールです。
焦らず、毎日同じ手順と同じ愛情を持って接し、「寝る」という行為を親子の信頼関係を築く時間として捉え直すことで、自立寝への道は必ず開けます。
- 『支配ではなく信頼』の哲学:子どもの自己決定権を育むアドラー心理学に基づく声掛け👉️




コメント