トラブルは「成長のための最高の機会」
姉妹のケンカが始まると、ついつい「お姉ちゃんなんだから譲りなさい」「仲良くしなさい」と介入したくなるのが親心。しかし、その介入が子どもの自立を妨げているかもしれません。
我が家では、4歳と2歳の姉妹のケンカに、パパは原則介入しません。なぜなら、このトラブルこそが、社会性や協調性、そして真の感情のコントロールを学ぶ最高のトレーニングだと考えているからです。
ケンカに「介入しない」ことが最高の育児である理由

僕が元看護師・現外壁塗装パパとして、あえてケンカを見守る姿勢を貫く3つの理由です。
理由1:社会性の予行演習
幼稚園や学校、社会に出れば、親は誰も助けてくれません。姉妹間のケンカは、実社会で起きるトラブルの縮図です。ここで自力で解決する「挑戦の過程」を経験させることが、将来の人間関係に直結します。
理由2:「自分で解決できる」という自己肯定感
親が介入すると、「パパ・ママがいないと解決できない」という依存心が生まれます。自力で解決できた時こそ、「自分たちの力で困難を乗り越えた」という強烈な成功体験となり、自己肯定感を育みます。
理由3:感情と言葉の調整力
「感情コントロール編」で感情の言語化を学んだ子どもたちが、次は相手の感情を読み、自分の要求を言葉で通すという高度な調整力を磨く場になります。
感情コントロールについてはこちら!
パパ流・姉妹ケンカ「自力解決」を促す3つの法則

「介入しない」と「放置」は違います。パパは審判ではなくコーチとして、子どもたちが自力で解決できるように誘導します。
法則1:危険と「不一致」を明確に分ける(介入の境界線)
介入する場合: 安全に関わる行為(叩く、噛む、投げつけるなど)が発生した場合のみ、直ちに介入します。これは子どもたちの生命を守るという看護師の視点から譲れないルールです。
見守る場合: 意見の不一致(おもちゃの取り合い、場所の奪い合いなど)は、子どもたち自身の問題として見守ります。
法則2:結果でなく「調整の過程」を褒める
BLWやトイトレと同様に、「誰が譲ったか」という結果ではなく、解決に向けて努力した過程を褒めます。
実践内容: 「おもちゃを貸しなさい」とは言いません。代わりに、「今、お姉ちゃんの顔を見て話そうとしていたね。その話そうとした頑張りがパパは嬉しいよ」と、解決に向けた小さな行動を褒めます。
狙い: 譲った方だけでなく、譲らなかった方も含め、両方がポジティブな気持ちで次の話し合いに進めるように促します。
法則3:パパは「代弁者」になる(論理的な思考をサポート)
言葉が詰まってケンカが進まなくなった時、親は中立的な代弁者として、状況を整理する言葉を与えます。
実践内容: 「お姉ちゃんは『まだこれで遊びたい』と意見を言っている」「妹ちゃんは『今すぐ使いたい』と感情を表現している。じゃあ、二人は次にどうする?」
狙い: 感情的になっている子どもたちの意見や感情に「名前をつけて整理する」ことで、論理的な思考をサポートし、自力で解決策を考えさせるように促します。
まとめ:家族というチームの成長
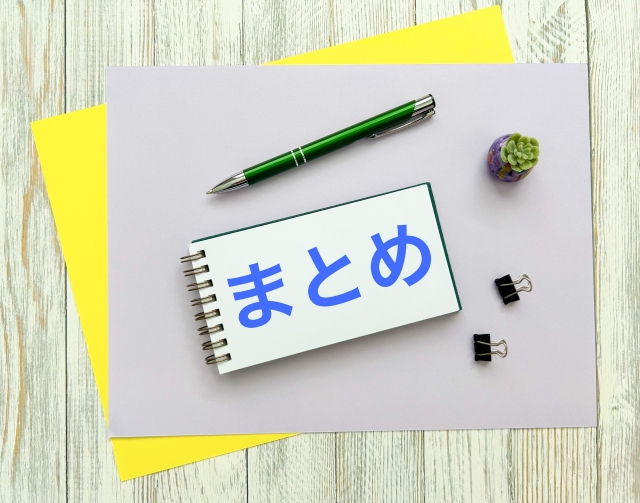
姉妹育児で起こるトラブルは、パパが「挑戦」を教えている証拠です。
ケンカの度に、子どもたちは感情と言葉、社会性という3つの力を同時に鍛えています。
親がすべきことは、子どもたちの自力解決能力を信じて、温かく見守ることです。
- 『支配ではなく信頼』の哲学:子どもの自己決定権を育むアドラー心理学に基づく声掛け👉️





コメント